はじめに
不妊治療の選択肢のひとつである体外受精(IVF:In Vitro Fertilization)。自然妊娠が難しい場合に用いられる治療法ですが、「具体的にどのような流れなのか?」「どんな人が対象になるのか?」など、基本的なことを知っておきたい方も多いのではないでしょうか。
本記事では、体外受精の基本情報を分かりやすく解説します。
1. 体外受精とは?
体外受精とは、体外で卵子と精子を受精させ、受精卵(胚)を子宮に戻す不妊治療の一つです。自然妊娠では、卵管内で卵子と精子が出会い受精しますが、何らかの理由でそれが難しい場合に、人工的に受精をサポートするのが体外受精です。
2. 体外受精の流れ
体外受精は、以下のような流れで進みます。
① 卵巣刺激・排卵誘発
排卵をコントロールするために**ホルモン剤(注射や内服薬)**を使用し、複数の卵子を育てます。
② 採卵
成熟した卵子を取り出すために、経腟超音波ガイド下で針を使って卵巣から卵子を採取します。
③ 採精・精子の準備
採取した精子を洗浄・濃縮し、受精しやすい状態にします。
④ 受精
採卵した卵子と精子を体外で受精させます。受精方法には、以下の2種類があります。
• 通常体外受精(IVF):シャーレ内で卵子と精子を自然に受精させる方法
• 顕微授精(ICSI):1つの精子を細い針で卵子に直接注入する方法
⑤ 培養
受精卵を数日間培養し、細胞分裂を確認します。成長の過程で胚盤胞まで発育すると、着床の可能性が高まります。
⑥ 胚移植
培養した胚を子宮に戻します。新鮮胚移植と凍結胚移植の2種類があります。
⑦ 妊娠判定
胚移植から約10日後に血液検査(hCG検査)を行い、妊娠の有無を確認します。
3. 体外受精が適応されるケース
体外受精は、以下のようなケースで選択されることが多いです。
• 卵管因子(卵管閉塞・卵管癒着など):卵子と精子が自然に出会えない
• 男性不妊(精子の数が少ない・運動率が低いなど):自然受精が難しい
• 排卵障害(多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)など)
• 原因不明不妊:タイミング法や人工授精で妊娠しない
• 高齢不妊:年齢的に妊娠率を高めるため
4. 体外受精の成功率と年齢の関係
体外受精の成功率は年齢とともに低下します。
日本産科婦人科学会(JSSRM)のデータによると、
• 30代前半:成功率 約30~40%
• 35歳を過ぎると徐々に低下
• 40歳以上:成功率 10~20%以下
特に卵子の質の低下が影響するため、年齢が上がるほど胚の着床率も下がる傾向があります。
5. 費用と助成制度について
体外受精は高額な治療ですが、2022年4月から保険適用となりました。
• 保険適用(一定条件あり):1回あたり10~30万円程度
• 自由診療(保険外):1回あたり30~60万円以上
また、自治体によっては助成金制度があるため、費用面の負担を軽減することも可能です。
6. 体外受精のリスクと注意点
体外受精にはいくつかのリスクもあります。
• 卵巣過剰刺激症候群(OHSS):卵巣が過剰に刺激され、腹水やむくみが出る
• 多胎妊娠のリスク(移植する胚の数による)
• 精神的・身体的ストレス(ホルモン治療や待機期間の負担)
そのため、医師とよく相談しながら治療を進めることが大切です。
まとめ
体外受精は、不妊治療の中でも高度な技術を必要とする治療法ですが、多くのカップルにとって妊娠の可能性を高める方法です。
✅ 基本的な流れ:採卵 → 受精 → 培養 → 胚移植
✅ 対象となる人:卵管因子・男性不妊・高齢不妊など
✅ 成功率は年齢により変化
✅ 費用は保険適用もあるが、助成制度の活用もおすすめ
不妊治療は一人ひとり状況が異なるため、焦らず自分に合った方法を見つけることが大切です。
あなたの妊活が実を結ぶように、少しでも参考になれば幸いです。
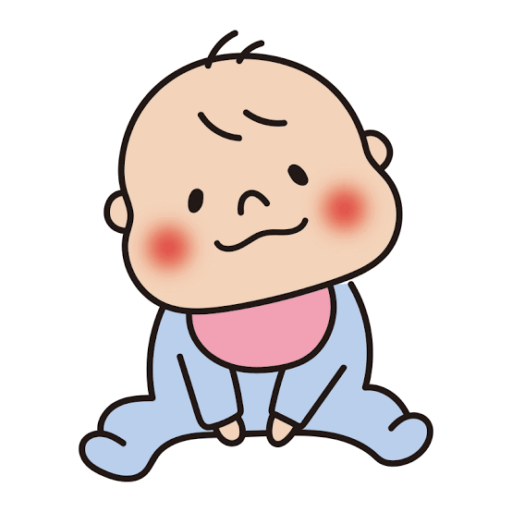

コメント